
2025年8月5日、2025年度最初のGXスタジオが開催されました。
GXスタジオは、GXリーグ参画企業が高い関心を寄せるテーマを取り上げ、最新情報の共有や業界の垣根を超えた自由な対話を通じて理解・交流を深める場として、初年度から継続的に開催しているものです。第1回のテーマは「気候関連情報開示」。情報開示をテーマに取り上げるのは通算3度目となりますが、世界的に開示規制強化が進む中、企業はさらなる対応を求められています。東京の会場には約60名、オンライン配信には約130名と多くの企業が参加し、課題意識の高さがうかがえました。

開会の挨拶に立った経済産業省 GXグループの高橋啄朗氏は、気候関連情報開示の中でも、とりわけサプライチェーンのスコープ3に対する取組がGX推進において極めて重要であることを強調。その上で、GX市場の創造に取り組む企業の持続的成長を促すべく、GXリーグ内にサプライチェーンでの取組のあり方に関する研究会を設置したことに言及しました。「次年度以降のGXリーグをより進化させるため、現在検討を進めているところ。参画企業のみなさまには、この場を機会に、活発に意見交換し、スコープ3の取組をいっそう浸透させていただきたい」と期待を寄せました。
イベント前半にはプレゼンテーションが行われました。経済産業省 環境金融室より「スコープ3ガイドブック」策定に向けた検討状況について説明があったほか、参画企業からキリンホールディングスと日清食品ホールディングスが登壇し、各社の取組を紹介しました。
経済産業省 環境金融室によるプレゼンテーション
スコープ3排出量の開示要請は年々高まり、TCFD提言(2017年)、補足文書(2021年)、IFRS基準(2023年)と徐々に強化される動きがある中で、日本でも時価総額に応じて2027年3月次から順次、サステナビリティ開示が義務化される予定です。国内における気候変動関連の情報開示をめぐっては、2019年5月に民間主導の「TCFDコンソーシアム」が発足し、「グリーン投資ガイダンス」や「TCFDガイダンス」などを策定してきました。昨今の流れを受けて、コンソーシアムでは現在「スコープ3ガイドブック」策定に向けた議論が進められています。

経済産業省 GXグループ 環境金融室の森本有香氏は、「スコープ3は大企業のみならず中小企業も含めたサプライチェーン全体の取組を促し、GX製品市場の創造拡大につながるという意義もある」と述べ、取組が投資家から適切に評価されることで企業の戦略的意義を生み出すことにもつながるとの見方を示しました。一方で、スコープ3をめぐっては、事業会社にとってデータの収集や算定に大きな負担がかかることや、投資家にとっては企業間比較による投資判断が難しいことなどが課題となっています。「スコープ3ガイドブック」はこうした課題を踏まえ、①過大なコストや労力がかからず、意思決定的に有用な開示とは何か、②開示情報から何を読み取り投資判断に役立てるべきか、という視点から議論してまとめられる予定です。2025年7月の中間報告では、事業会社と投資家それぞれにとっての課題・意義を整理し、取組の方向性が示されました。
「開示のための開示ではなく、バリューチェーン上の削減を促すことができる、真に意味のある開示を目指していく」と森本氏。ガイドブックには、業種別(電機・自動車・小売・不動産・食品・商社)のガイドラインやベストプラクティスに加え、開示をより有用なものにするために活用できる指標(「削減実績量」「削減貢献量」など)に関するコラムなども盛り込むこと方向で、2025年度内に完成版が公表される方針である旨伝えました。
参画企業によるプレゼンテーション
キリンホールディングス
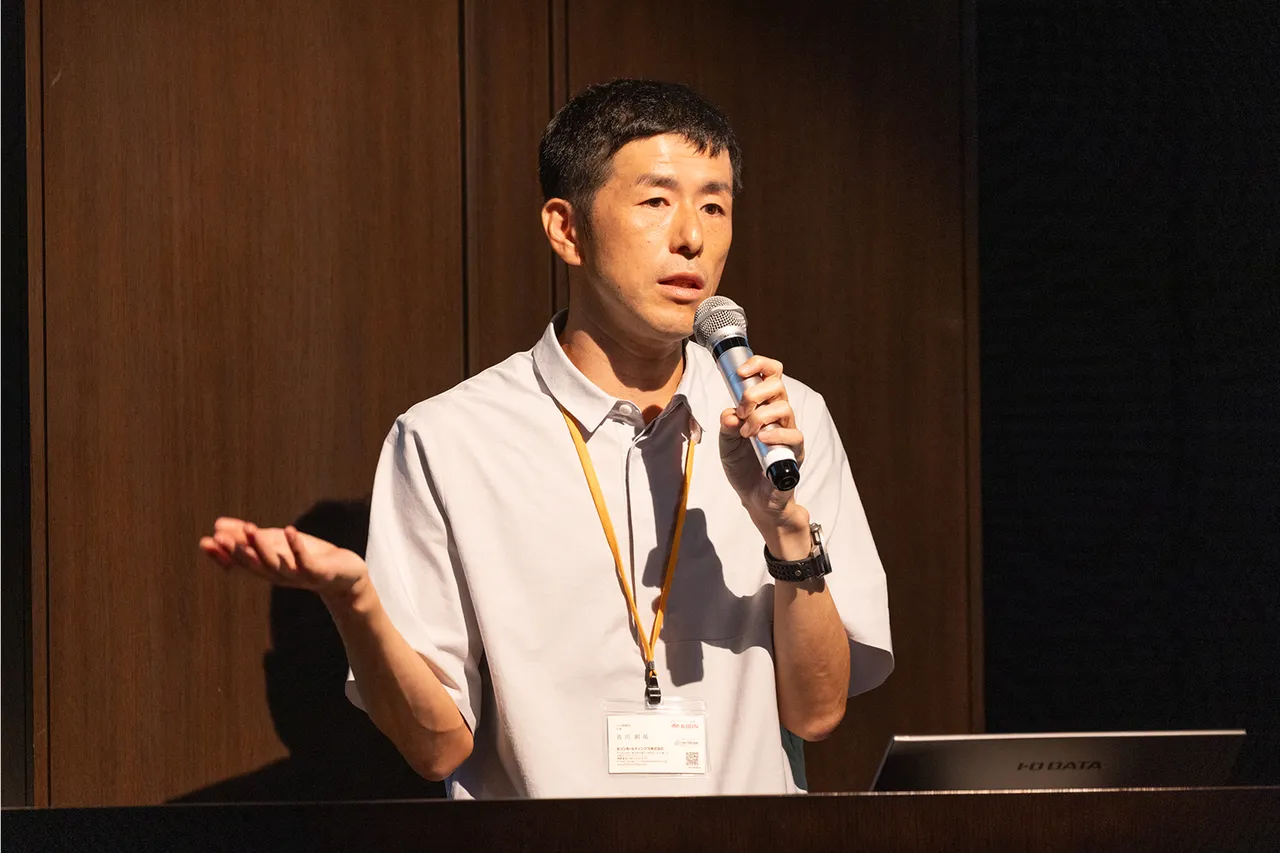
飲料・酒類、医薬、ヘルスサイエンス事業などを手がけるキリンホールディングスは、M&Aを通じた事業領域拡大に伴い、サプライチェーンも広がっています。すべての事業活動は自然資本や健全な生態系のもとに成り立つとの認識の下、同社は早くからGHG排出量算定に取り組んできました。削減目標としては、SBTの認定を受け、2019年を基準年としてスコープ1、2は2030年までに50%削減、スコープ3は34%削減を目指しています。現在はスコープ1、2で34%削減を達成しているものの、スコープ3は10%にとどまっています。
同社CSV戦略部の吉川創祐氏は、「スコープ3は削減の前に把握という壁がある。サプライヤーやパートナーと一緒に取り組む領域なので、コンセンサス作りを丹念に進めている」としながら、自社の取組としては、大きな排出源となっている容器包装の軽量化や輸送方法の改善など、経済的価値につながるものから優先的に進めていると説明。現時点ではグループ全体で排出量の算定方法を統一することは難しく、また、近年、開示項目が増える流れにある中で、データとエビデンスの収集方法や効果測定方法など、課題は山積しているといいます。吉川氏は、サプライチェーン全体でコスト負担を理解し合うことの重要性を強調し、消費者を含めた理解促進に取り組む必要があるとしました。
こうした取組の数々を企業価値につなげる試みとして、同社は毎年発行する環境報告書の情報を経営判断に活用するために、さまざまな会議体で使用し始めています。また、生活者や従業員に向けてサステナビリティに関するメッセージを積極的に発信。吉川氏は、「企業としての姿勢やストーリーを伝えていくことが、その先の企業価値の向上につながるのでは」と期待を込めました。
日清食品ホールディングス

カーボンニュートラルとネイチャーポジティブの実現を同時に掲げる日清食品ホールディングスは、環境戦略を中長期成長戦略の柱のひとつに位置付け、グループ全体で取組を推進しています。SBT認証を受け、1.5℃目標を意識したチャレンジとして、資源の有効活用や電力・食材・包材のグリーン化に取り組んでいます。
スコープ1、2では、インターナルカーボンプライシング制度を活用した省エネ活動や再エネ導入拡大により、排出削減を強力に推進。将来的に再エネ調達の割合を100%に引き上げることを目指し、現在は約6割を達成しています。スコープ3では、他企業との共同配送や環境配慮型包材の使用、代替食技術の活用のほか、主な排出源となる原材料調達において、環境や人権に配慮されたRSPO認証パーム油の活用に力を入れています。同社経営企画部の斉藤圭氏は、「認証制度だけに頼らず、自ら手足を動かして取り組むことが求められる時代になっている」との認識を示し、東南アジア約800カ所で搾油工場周辺の環境破壊度を衛星モニタリングする取組や、インドネシアの小規模農家支援プロジェクトを紹介。将来的なスコープ3の削減につながる取組として続けていく方針です。
こうした非財務の取組をコストから価値へと転換していくため、同社では経済的価値の分析・可視化に加え、インパクト加重会計による社会的価値の定量化にも取り組んでいます。「社会インパクトを定量化することで、われわれ自身も認識していなかった、新たなビジネスの価値を発見できた」と斉藤氏は手応えを語り、実際の取組と企業価値につなげる分析を同時にバランスよく進めることで、取組の価値を最大化していきたいと意気込みました。
グループ交流で気候変動情報開示に関する問題意識を共有

イベント後半、会場では5、6人のグループに分かれてグループ交流を行いました。業種や立場の異なる企業同士でテーブルを囲み、途中席替えをしてメンバーを入れ替えながら、業界・業種ならではの課題や、今後自社で検討したい取組について自由に意見を交わしました。



ディスカッションの内容は、データの信頼性、第三者保証、社内連携、サプライヤーとの関係構築、情報開示に向けた追加投資の課題などさまざま。経済産業省や登壇企業の方々も加わり、お互いの意見に熱心に耳を傾けながら活発に議論する様子が見られました。
約60分間のグループ交流は大いに盛り上がり、あっという間に終了の時間となりました。閉会にあたり、事務局の佐藤より参加への感謝を伝えるとともに、「スコープ3の領域は課題が尽きないが、解決に向けて、企業間連携や業界横断的な取組が非常に重要。GXリーグとしても後押ししていけるよう、さまざまな機会を設けていくので、ぜひ今後もご参加ください」と呼びかけ、盛況のうちに幕を閉じました。